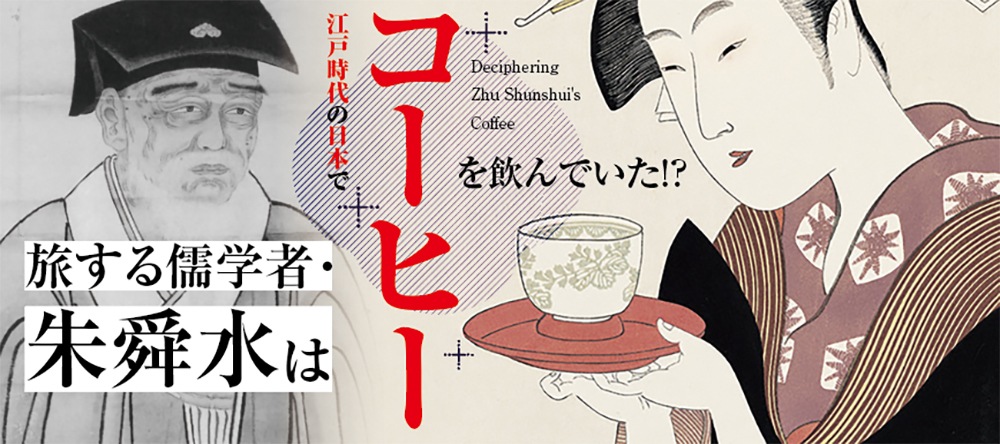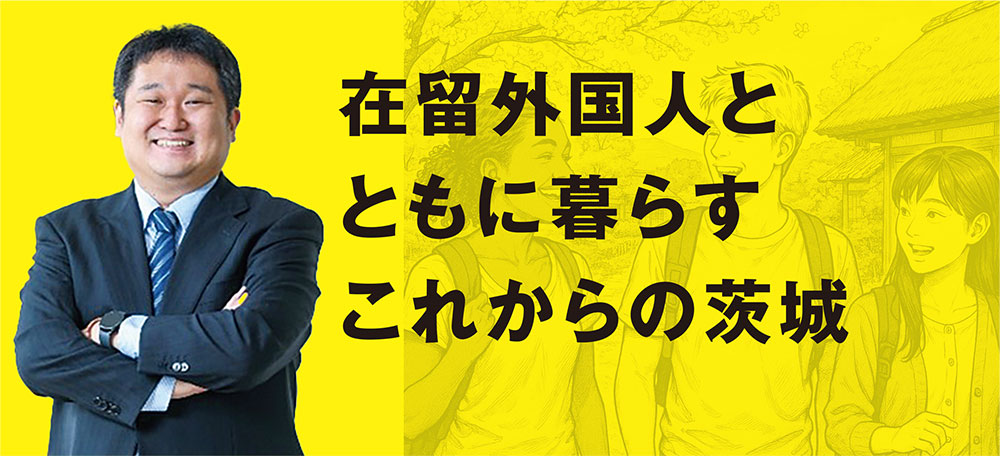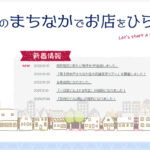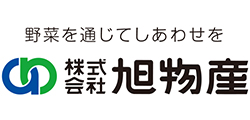木蘭酒家で不定期で開催している「水戸谷中の旦那衆」という交流会についてご紹介します。若者も当時の町の様子に興味を持ち、少しずつ動きが出てきています。
もはや蜃気楼! 昭和・谷中のにぎわい
二十三夜尊(さんやさん)桂岸寺の門前町・水戸谷中地区は、昭和の往時は押すな押すなの人だかりでにぎわっていました。しかし、今では人の気配も消えすっかり寂しい状態に。時代の変化といえばそれまでですが、そこにあった記憶まで風化してしまうのは、寂しいしもったいない。
そんな思いから、フリーライターの奥村かえでさんが中心になって、谷中地区で商いをしてきた人や長年暮らしてきた人から「まちの記憶」を聞く。その企画が「水戸谷中物語」。さらに、そうした人たちを呼んで、若者も交えて話をする交流会が「水戸谷中の旦那衆」です。
「まちの記憶」を聞く若者たち
この企画は茨城大学のゼミでも取り上げられており、学生が「まちの記憶」に触れる貴重な機会にもなっています。若者たちからすれば、活気に包まれた商店街というのは蜃気楼のように感じるでしょう。本当にそんなことがあったのだろうか!?と。
そんな茨城大学の先生が中心となって以前開催したイベントに、少しずつ学生たちもインスパイアされていきました。そして、昨年から「続・水戸谷中の旦那衆」が開催されています。7月16日には、茨城大学のサークル「CO-Cui」が主体となって木蘭酒家で開催。大学生と地元の人たちを合わせて約10人が参加しました。
活動発表と交流会。企画は3部構成
企画は3部構成で、第1部では同サークルから、あじさいまつり期間中に行った「水戸谷中フェスティバル」の活動報告が行われました。あじさいまつりの来場者向けに①お土産販売、②しおり作り体験会ーを行ったとのこと。
①お土産は地元企業と連携して販売。これを通じて観光客と交流を楽しんだそうです。また②しおりづくりは、あじさいまつりの思い出として手元に残るモノを作ってもらいたいと企画。紫陽花のドライフラワーなどを使って、観光客たちがオリジナルしおりを作成しました。

第2部は、大学生と旦那衆の交流会。木蘭酒家のフードとドリンクを楽しみながら、会話に花を咲かせました。ここで登場したのが昭和30年代の地図や過去に同地域の商店街が作成した観光マップで、さまざまな貴重な話をしてくれました。一方で、大学生たちの活動を見て、地元としても朝市など新しい取り組みを始められないかと未来に向けた話題も出ました。
第3部では、谷中で長年暮らす人たちの聞き書きを行い、本を出版するプロジェクト「水戸谷中物語」の事業進捗に関する報告。2024年に奥村さんが茨城大学の学生とともに20人を超える谷中の人にインタビューを行ってきました。
この日は、インタビューの進捗報告だけでなく本のデザイン案も参加者に紹介。奥村さんは「あえて谷中の人の語りを断片的に紹介する構成。余白から、昔の谷中の空気感や音、においなどを想像してほしい」と話しました。
「谷中の盆踊り」に復活の芽!?
余談ですが、9月7日に恒例の「水戸浪漫三夜祭」が開催され、そこで盆踊りが披露されました。「谷中の盆踊り」とえいば、 かつては水戸を代表する独特の盆踊りでした。その伝統がまた復活するのでは!? そんな期待感が高まった夏の夜でした。